所属部署 国際グループ
氏名:磯村計郎
BOPとはBase Of the Economic Pyramidの略で、世界資源研究所および世界銀行グループの国際金融公社が2007年に共同発行した「THE NEXT 4 BILLION」の定義によれば、世界中の人々を所得階層で分類したピラミッド(図表1)の底辺に位置する年間3,000ドル未満の所得で暮らす低所得者層を指します。BOPの人口は世界で約40億人にのぼり、とりわけ中国とインドを含むアジアに過半が存在しています(図表2)。このBOPの家計所得を総計すると、PPP(購買力平価)ベースで年間約5兆ドル(図表3)と推計されており、BOPは非常に大きな潜在的市場の一つとみなされつつあります。
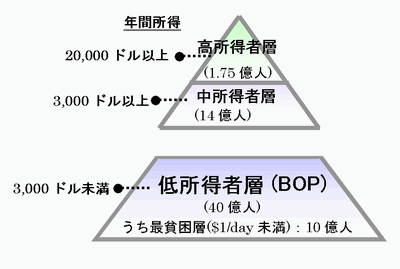
図表1.世界の所得階層(2007年)
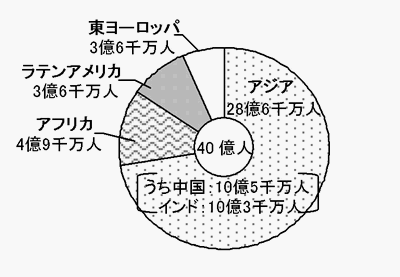
図表2.BOPの地域別人口
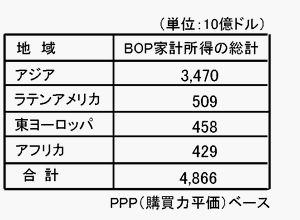
図表3.BOPの地域別家計所得総計
資料:「THE NEXT 4 BILLION」より(総研)作成(図表1〜3とも)
これまで経済活動から取り残されていたBOPは、先進国政府の援助対象か、企業のCSRの一環としての援助対象と捉えるのが一般的でした。しかし、近年、欧米企業において企業の本業を活かして利益を確保しながらも、BOPに雇用の機会を創り出して生活レベルを向上させ、貧困の低減を実現するという、ビジネスと社会貢献を両立させた成功事例が出ていることから注目を集めています。その特徴は、従来のような一方通行の援助ではなく、企業とBOPが協働でWIN-WINの関係を創り出していくところにあります。
BOPは、必ずしも怠惰によって貧困に陥っているわけではなく、働く意欲があっても雇用機会が不足していたり、適正な労働賃金が支払われていないなど、貧困を余儀なくされている外部環境上の制約が要因の大半を占めます。例えば、自ら事業を起こしたくても、わずかな自己資金もなく、銀行融資も期待できないため高利貸しから借金する結果、いつまでも返済できない悪循環に陥ります。農作物や工芸品を売りたくても、市場が遠隔地にあるため、輸送手段を持たないと市場価格も把握できません。その結果、仲介業者から多額の中間マージンを搾取され手元に資金が残らない状況もあります。
このように貧困であるがゆえに不適正な対価を支払わざるを得ず、結果貧困から抜け出せない不利な状況は「poverty penalty(貧困ペナルティ)」と呼ばれ、多くのBOP地域で見られる現象です。さらに、子供が日々の糧を得る労働力として使われ、教育機会を逃すことも貧困の原因として見逃すことはできません。このような社会構造上の制約がもたらす貧困の悪循環から抜け出すには、各国政府機関の政策対応や、ODAなどの海外援助が必要ですが、それだけでは限界があります。そこで、民間企業がBOPへ技術やサービスなどを提供することにより、貧困ペナルティのような制約要因を取り除き、BOPの生活を向上させることができれば、そこにBOPビジネスという大きなビジネスチャンスが生まれると考えられます。
日本企業のBOPビジネスへのトライ事例として、ヤマハ発動機(株)がアジア各地でモニター展開する小型浄水プラント「クリーン・ウォーター」プロジェクトを挙げることができます。この浄水プラントは、化学薬品を使用せずに自然の仕組みを利用し、河川などの汚れた水を微生物を生かした砂のフィルターを通して緩やかにろ過するシステムを採用し、薬品を使う浄化システムに比べてメンテナンスが容易で低コストなシステムとなっています。同社は、この浄水プラントの建設を通して上水道の整備されていない地域にクリーンな水を供給することをミッションに掲げており、これは国連ミレニアム開発目標(MDGs)で掲げられた安全な飲料水へのアクセス改善にも貢献するものです。また、この浄水プラントを用いてろ過した水の供給は、村落を主体とした自治運営によって行われるよう企画されていて、現地の自立を支援するビジネスモデルと言えます。本プロジェクトは、国連開発計画(UNDP)の"持続可能なビジネス育成プログラム(GSB*1)"を活用し、インドネシアにおいて国連開発計画(UNDP)とヤマハ発動機(株)による共同検証作業が行われております。
先進国市場が伸び悩んでいく一方で、BOP市場に目を向けると成長の伸びしろが大きい40億人の巨大なマーケットが広がっています。今後日本企業が持続的な成長を維持するためにはBOP市場をターゲットに定めることも選択の1つです。しかし、BOP市場に参入する場合、先進国とは市場ニーズも購買力も異なるため、プロダクトアウト型発想ではビジネスとして失敗を招く恐れがあります。他の成功事例を見る限り、BOP市場で成功を収めるためには、BOPをビジネスパートナーと見なし、現地のニーズに適合した技術やサービスを協働して創りあげているようです。また、BOPを対象としたビジネスは短期的には利益が出しにくいビジネスです。しかし、長期スパンで考えれば企業がBOPの所得向上の一端を担い、BOPがより上位の所得階層へ移行して購買力を上げた時には、企業に利益が還流されることが期待できます。いずれにせよ、日本企業がBOPビジネスに取り組むには、BOPへの社会貢献は社会から与えられたミッションの1つであると、確固たる信念を掲げて臨む必要があるでしょう。
機関誌「日立総研」、経済予測などの定期刊行物をはじめ、研究活動に基づくレポート、インタビュー、コラムなどの最新情報をお届けします。
お問い合わせフォームでは、ご質問・ご相談など24時間受け付けております。