所属部署 産業グループ
氏名:村井祥之
「企業の利き手」とはハイテク製品のマーケティング理論「キャズム」(Crossing the Chasm)を提唱したことで知られるジェフリー・ムーア氏がHarvard Business Review 2005年12月号(日本語版はダイヤモンド・ハーバード・ビジネス・レビュー2006年3月号)の論文「Strategy and Your Stronger Hand(すべての企業に「利き手」がある)」で提唱した概念であり、企業を大きく「複雑系モデル」と「大量生産モデル」の二つに分類できるというものです。
企業の戦略論としてはケネス・アンドリューが提唱した「SWOT」分析、マイケル・ポーターの「ファイブ・フォース」分析などが有名ですが、「企業の利き手」は企業のタイプを大きく二つに分けることにより、企業の強みと弱みを直感的に理解するのに有効な手法です。
「複雑系モデル」が当てはまる企業とは、顧客数が数千規模で年間取引の回数は少ないが、一回の取引金額は数千万から数億円あり、主に企業顧客向けにカスタマイズされた製品・ソリューションを提供する企業のことです。
一方、「大量生産モデル」が当てはまる企業とは、顧客数が数百万規模で年間取引回数は数十回から数百回、一回の取引金額は小額であり、主に一般消費者に向けた低価格の製品・サービスを提供する企業のことです。
上記のモデルの特徴をまとめると以下のようになります。
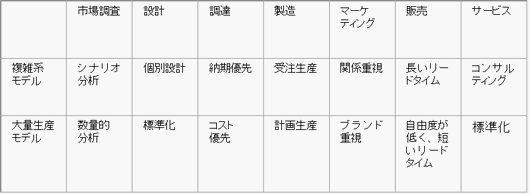
資料:Harvard Business Review "Strategy and Your Stronger Hand"より(総研)作成
ムーア氏は一つの企業が両方の利き手を追い求めてもうまくいかず、最終的には「複雑系モデル」か「大量生産モデル」のどちらかを選択せざるを得ないと主張しています。例えば「複雑系モデル」の企業の場合、ある製品を製造する際に、コストより個々の顧客のニーズを優先する場合が多く、大量生産モデルの企業に対してコストで優位に立つことは難しいからです。
上記論文ではGeneral Electric Company(GE)の例を取り上げています。GEは電球のような「大量生産モデル」の事業と航空機エンジンのような「複雑系モデル」の事業の両方をおこなっています。当然のことながら社内では事業部を分けて運営していますが、「複雑系モデル」の事業の方が規模も大きく、収益も上げているため、著者は将来的にはGEは企業全体が「複雑系モデル」に移行するであろうと予想しています。(その後、GEは電球などのコンシューマー事業の分離独立を含む戦略オプションを検討する意向を表明)
以上のムーア氏の意見に関しては、必ずしもすべての企業に当てはまるものではないという反論は容易に可能ですが、新規事業の開拓やM&Aにおいて決断する際の判断基準のひとつとして考えることに意味があるのではないかと考えます。企業の新規投資案件がキャッシュフローなどの利益指標を重視してしまいがちであり、バランスを取る意味で自社の「利き手」を評価軸として考慮する価値があると考えます。
機関誌「日立総研」、経済予測などの定期刊行物をはじめ、研究活動に基づくレポート、インタビュー、コラムなどの最新情報をお届けします。
お問い合わせフォームでは、ご質問・ご相談など24時間受け付けております。