所属部署 研究第三部
氏名:吉川武志
「銀行・証券間のファイアーウォール規制(以降「銀証ファイアーウォール規制」という)」とは、1993年施行の「金融制度改革法」における業態別子会社方式による銀行・証券の相互参入解禁の際に導入された規制です。もともとわが国では、米国で銀行・証券間の兼業禁止を定めたグラス・スティーガル法(1933年)*1を参考に、戦後制定された証券取引法第65条で銀行本体での証券業務を禁止していました。これはリスクの高い証券業務を禁止することによる銀行の健全性確保や、資金提供者としての銀行の優越的地位濫用(らんよう)を防止することなどを目的に制定された規制です。 銀証ファイアーウォール規制は、銀行が子会社方式で証券業務への参入を可能にするなかで、引き続きこれらの弊害を防止するために導入されました。 同規制の導入以降、金融サービスの利便性向上の観点から段階的に緩和が進められています(1999年店舗共有、共同訪問解禁ほか)が、証券取引法を受け継いで2006年に新たに制定された金融商品取引法でも同規制は維持されています。現在では同法を中心に主に以下のものが規制されています。
わが国の銀証分離は、米国のグラス・スティーガル法をモデルとしたものですが、米国では80年代より、実際の銀行間買収進展等により徐々に規制が崩れはじめ、1987年には同法の一部緩和(銀行持株会社の子会社における一定割合以下の証券引受業務解禁)に伴い、銀証ファイアーウォール規制が導入されました。
その後1997年に銀行持株会社子会社の証券引受基準の緩和*7や、非公開顧客情報の共有制限の撤廃等さらなる規制緩和がなされ、また1999年にはグラム・リーチ・ブレイリー法が発効され大幅な規制改革が実現しました。これら一連の規制緩和は、IT・金融技術の進展やグローバル化による競争激化および市場の変化に追従する形で進んでおり、米国金融産業の国際競争力強化に寄与したと評価されています。
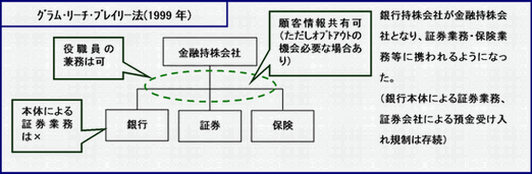
また「証券会社、銀行等および保険会社に対し、利益相反管理体制の強化」の義務付け、および「銀行等の優先的地位を濫用した証券会社による勧誘の禁止等」の措置があわせて強化されることとなっています。これらについての行政当局の規制手法は、以前からの「ルール・ベースの監督」に加えて諸外国で主流になりつつある、いわゆる「プリンシプル・ベースの監督」の導入を図る方向になっています。
「プリンシプル・ベースの監督」とは、従来の業務ごとに細分化された当局による管理規制方法と異なり、証券会社や銀行等に弊害防止のためのガイドラインに基づいた内部管理体制整備を法令上義務付け、それを当局が適切にモニタリングし、実効性を確保するという新たな規制の枠組みであり、金融機関としては経営の自由度が確保される一方、自己責任に基づく内部統制と厳しい規律付けが必要となってきます。
今後一層の金融サービスの多様化が進むなかで、一層の自己責任原則に基づいた自立的な内部統制体制の確立、強化が求められると考えられます。
2007年6月19日閣議決定された「経済財政改革の基本方針2007」に盛り込まれた「銀証ファイアーウォール見直し」の提言を受けて、同年12月21日金融庁が発表した「金融・資本市場競争力強化プラン」で規制緩和の方向が打ち出されました。
同プランでは規制見直しの狙いを以下のように述べています。
利益相反による弊害や銀行等の優越的地位の濫用の防止の実効性を確保するとともに、金融グループにおける業務の相互補完や効率化によるシナジーの発揮を通じて顧客利便の向上や金融グループの統合的内部管理の要請に応える観点から、銀行・証券・保険間のファイアーウォール規制を見直し、新たな枠組みを導入する
金融庁 「金融・資本市場競争力強化プラン」P.10より抜粋
具体的には前述のファイアーウォール規制項目のうち、(1)役職員の兼職規制の撤廃、(2)法人顧客情報に関する非公開情報の授受の制限緩和(顧客が不同意を表明しない限り、グループ内で情報共有を認める)について見直しをおこなうものとされております。
このうち、(1)については、例えば金融機関の人的経営資源の効率化(2008年3月4日国会に提出済み)、(2)については法人客に対する質の高い総合金融サービスの提供が期待されています。
なお、金融審議会では「非公開情報の授受の制限」のうち個人顧客情報の共有、「発行体向けクロスマーケティング規制」、「主幹事引受規制」といった規制についても議論がありましたが、今回緩和は見送られました。
機関誌「日立総研」、経済予測などの定期刊行物をはじめ、研究活動に基づくレポート、インタビュー、コラムなどの最新情報をお届けします。
お問い合わせフォームでは、ご質問・ご相談など24時間受け付けております。